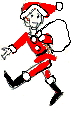人はみな、自分の子供の名前を考える時、詩人になるという。もうひとつ、私たちが詩人になる時があるとすれば、それは「サンタクロースって、本当にいるの?」と子供たちに聞かれた時だろう。親たちはみな、子供たちの夢を壊さないためにはどう答えればいいかと思いを巡らせるはずだ。
うちの息子は五歳の時、サンタクローズを心から信じていた。七歳になると好奇心をいっぱいにして「どうして欲しいものがわかるの。サンタさんはどこに住んでるの。うちにはどうやって入ってくるの」と、親を質問攻めにした。九歳の息子には知恵がついて「この包装紙、うちにあったのと似てる」と言って親をあわてさせた。十一歳の息子は「サンタさん、いつまでプレゼントを持ってきてくれるかな」とつぶやき、私が「サンタさんを信じている間は持ってきてくれるんじゃないの」と言うと、「やったー、ぼく信じてるからね、持って来てって言っといてね」と、念を押した。
そして一九九六年のクリスマス、十二歳の息子にサンタクロースはやって来なかった。「中学生になって、運賃も大人の料金を払うようになったんだから、もうサンタさんは来ないと思うよ」と言ってあったのだけれど、それでもクリスマスの朝、息子はほんの少し、サンタからのプレゼントを期待していたらしい。
その後、私たちはサンタクロースについて何も話していない。何も語らないことが、彼が大人になることを受け入れたしるしのようにも思える。「サンタクロースを信じる」という暗黙の共犯関係を崩したことへの無言の抗議のようにも思える。しかしともかく、私たちはサンタが来ない特別な朝を迎え、夫と私はサンタクロースになるという楽しい時間を失った。
「嘘をついてはいけない」と教える世界中の親たちが、年に一度つく悪気のない嘘。この嘘について、今、息子がどう考えているのかはわからない。でもきっと、何かすっきりしないものがあるだろう。もし彼が、「サンタクロースなんて本当はいないのに、なぜ嘘をついたの?」と聞いてきたら、どう答えたらいいだろう。一九八七年の冬、ヴァーニジアという名の八歳の女の子が、シカゴ・サン紙の記者に手紙を書いた。「親愛なる記者様、サンタクロースは本当にいるのでしょうか?」
記者は新聞紙上に、こう返事を書いたという。「ヴァージニア、サンタクロースはいます。目には見えないけれど、愛や、友情や、優しさが私たちの心の中にあるように、サンタクロースは、私たちの心の中にいるのです」
これは、クリスマスの度にテレビやラジオで紹介され、絵本にもなっている有名な話なのだが、この話が百年近くも語り継がれてきたのは、多くの親が 「サンタークロースは本当にいるの?」という難問に苦労して答えてきたからだろう。
そう、私は息子の問いに、こう答えよう。「サンタクロースはいるよ。なぜならサンタクロースとは、親の愛だから。プレゼントがなくても親の愛を十分に感じ取れるほどキミの心が成長したから、サンタは来なくなった。でもその代わり、キミはこれからサンタになる楽しみを味わえるんだよ」と。